一年のうちで2月はイベント、行事が比較的少ないイメージがある月です。でも調べてみると、季節に関係する伝統的な行事やイベントがたくさんあることが分かりました。
そんな2月のイベント、行事、記念日等をまとめてみましたので是非ご覧下さい。
スポンサーリンク
節分(2月3日前後)

日本の伝統行事である節分と言えば2月3日、と思われる方も多いと思いますが、実は年によって前後一日変わる事があります。
これは、節分とは実は立春の日の前日を指すからです。立春の日に変動があることはこの次の章でご覧下さい。
節分の歴史は古く、平安時代に宮中で行われた追儺儀式に起源があります。当時は弓矢を持った上級貴族が、鬼に扮した下級貴族を追い払って厄除けをする儀式が行われていました。
現代では形を変え、家庭等で豆をまいて鬼を追い出し、福を呼び込む儀式になっています。
また、近年では恵方巻きが定着しつつあります。年ごとに決められた方角(恵方)に向かって、寿司の太巻きを無言でほおばるイベントですが、コンビニエンスストアから人気に火が付いたと言われています。
立春(2月4日前後)

旧暦ではこの日を一年の最初の日とし、春が始まる事になります。
天文学的には、太陽の角度が315℃になる日と定められています。そのため、現在の暦に当てはめると年により2月3日だったり、5日になったりします。
また、立春の日に「立春大吉」と書かれた札を玄関先に貼っておく風習があります。「立春大吉」は左右対称で、縦に書くと裏側から見ても同じ文字が透けて見えますよね。
鬼が玄関から入ってきたときにふと振り返ると「立春大吉」の札が貼ってある。おっとあちらにも家がまだあったか、とばかりに玄関から出て行く、といった厄除けのお呪いです。
初午(2月最初の午の日)

「はつうま」と読みます。
京都の伏見大社に祀られる宇伽之御霊(うかのみたま)という神様が、初午の日に伊奈利山に降臨された日とされ、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全を祈祷する祭りが開催されます。
狐は稲荷の使いとされ、その狐の好物である油揚げをつかった料理としていなり寿司をこの日に作って食べる様になりました。
さっぽろ雪まつり(2月上旬)

毎年2月のビッグイベントといえばさっぽろ雪まつりです。様々な雪像群が並び、夜にはライトアップされる光景は圧巻そのもの。特にその年の話題をテーマにした作品として大雪像が中心に鎮座します。
雪像の作成には自衛隊も協力をしていることでも有名ですね。
会場周辺にはグルメの店舗も並びます。スープカレー、ジンギスカン、いかめし、焼き牡蠣、蟹甲羅焼きなど、北海道の旨いものがこのエリアに集結します。
子供も楽しめる体験エリアとして「つどーむ会場」も設置されます。100メートルの雪の滑り台に小さいお子さんも大はしゃぎします。
北方領土の日(2月7日)

1981年に閣議了解で定められた記念日です。1855年2月7日に江戸幕府と帝政ロシアとの間で日露和親条約が結ばれ、領土が確定したことに基づいて制定されました。
毎年この日に、東京都内で「北方領土返還要求全国大会」が政府、衆参両院、各党からの代表の出席の下行われ、講演会やパネル展示会などで賑わいます。
スポンサーリンク
針供養(2月8日)

長年、固い布地に通してきた針に対して「最後は柔らかいものに刺さって下さい」と供養をする伝統行事です。豆腐や紺にゃくんなどに使い古した針を刺して供養します。
各地の淡島神社(粟島神社)で2月8日に行われますが、関西を中心に12月8日に行うところもあります。それぞれの日に供養を行う寺社を以下にまとめます。
2月8日
淡嶋神社(和歌山市)、淡島神社(北九州市)、浅草寺(東京都)、荏柄天神社(鎌倉市)、太平寺(大阪市)
12月8日
幡枝八幡宮(京都市)、長浜八幡宮(長浜市)、武信稲荷(京都市)
両日開催
虚空蔵法輪寺(京都市)、天神社(徳島市)
建国記念の日(2月11日)

一般に「建国記念日」と言われることが多いですが、正しくは「建国記念の日」です。
日本という国は建国日が明確ではありません。そのため、古事記や日本書紀の記述から、初代天皇である神武天皇が即位した、旧暦紀元前660年1月1日を建国日と定めました。
明治時代にこれを新暦に改めたものが「紀元節」です。敗戦後、GHQの意向でいったんは廃止されますが、1966年に国民の祝日として「建国記念の日」と名を変え復活しました。
国会審議の際、「神話に基づいており、事実と認定できない」との意見と擦り合わせ、「建国そのものを祝う日」として「建国記念日」ではなく「建国記念の日」とした経緯があります。
バレンタインデー(2月14日)

誰もが知る日ですが、いつどのようにして始まったのかは意外と知られていません。元々はローマ帝国の時代、結婚と家庭の女神ユーノーに捧げる記念日でした。
また、同じローマ帝国で兵士の結婚は禁じられていましたが、命令に抵抗して密かに結婚式を行ってきたバレンタインという司祭がおり、キリスト教では後年、この人物を聖人として認定しました。
この二つの事象が組み合わさり、西洋の伝統行事として「聖バレンタインズデー」が成立してきました。
日本では製菓会社の販売促進キャンペーンとして女性から男性へチョコレートを渡す様になりましたが、始まりは昭和11年、昭和33年など諸説あります。
竹島の日(2月22日)

2005年に島根県議会により制定されました。島根県知事が竹島の所属所管を明らかにする告示を行った日の100周年としてこの日を記念日としました。







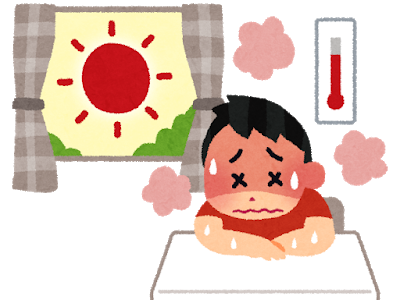




この記事へのコメントはありません。